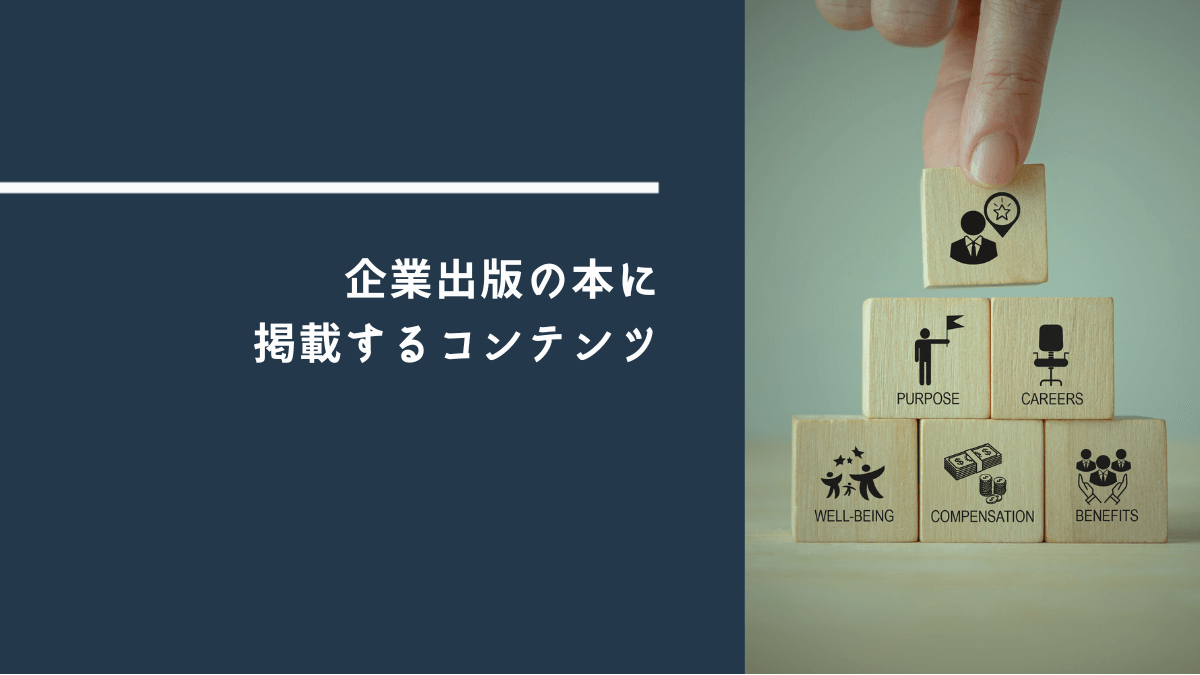企業出版の本にはどんなコンテンツを掲載すればいいの?
出版企画の方向性がある程度決まってきたら、次はどのようなコンテンツを掲載するべきかについて考えていくことになります。
そこで今回は、企業出版の本に掲載するコンテンツについて解説していきます。
ぜひご覧ください!
記事の目次
基本は事例が一番わかりやすい
どのカテゴリーの本であっても、できるだけあなたの会社独自の事例を掲載することをおすすめします。
もちろん、理論や原則は大切なので掲載する必要がありますが、理論ばかりだと論文を読まされているような感覚になってしまうおそれがあります。
守秘義務契約があるため、会社名などの固有名詞を掲載することは難しいかもしれませんが、それでも過去のサービス提供の事例は差別化につながりますし、読者もイメージしやすいなどメリットが多くあります。
経営者の話を聞いていると購入したくなる
仕事上、経営者から会社やサービスについての話を聞くことが多いのですが、経営者の話を聞いているといつの間にか「この会社に仕事の依頼をしたいな」と考え始めていることが非常に多いことに驚かされます。
会社で一番の営業マンは経営者という考え方がありますが、これには一定の説得力があります。
ただ、経営者が常に営業の現場に同席できるわけではありません。
だからこそ、経営者に話してもらったコンテンツを本に込めて営業社員が使えるようにしていくのです。
企業出版プロジェクトは経営者が中心となって取り組んでこそ効果的と考えましょう。
コンテンツの掲載順に困ったときは普段の営業の手順を参考にする
どんなコンテンツを掲載するかも大事ですが、加えてコンテンツをどのような順番で並べるのかについても頭を悩ませることが多いです。
この場合は、普段の営業を参考にしましょう。
最初は、業界全体の動向や課題を明確にするところからスタートして、それを解決するためにはどのような方法があるのかを説明し、最後に事例などを紹介していく…大まかにこのような流れが一般的です。
コンテンツの順序もざっくりと上記のような流れにするとわかりやすくなることが多いものです。
また、なんとなく流れを組み立てるのが難しいなと感じた場合には、見開きで一問一答のように、どこから読んでも読みやすい構成にしてしまうのも一手です。
読みやすい本を目指す
企業出版でつくった本はどのように読まれることが多いでしょうか?
参考書のように、勉強を兼ねて一生懸命読んでもらえるでしょうか?
それとも、小説のように本の世界に没頭して読んでもらえるでしょうか?
どちらも、正解ではありません。
企業出版でつくった本は、どちらかというとパラパラとページをめくりながら流し読みのように読まれることが多いのです。
逆に言えば、読むのに苦労する本、疲れるような本であれば、途中で読むのを断念されてしまいます。
コラム:こんな本は読みづらい!途中離脱されてしまう本
以下のような本は、読者が途中で読むのを諦めてしまう可能性が高くなるので避けるのが賢明です。
1.あまりに分厚い本
分厚い本は読むのが大変そうと感じる人が多いものです。
もちろん、読者が興味を持っている状態であれば読んでくれることもあるかもしれませんが、それほどの動機がなければ読み始めてもらうことが難しくなります。
小冊子のようにあまりに薄いのも考えものですが、できれば200ページ以内くらいに抑えて分厚くなりすぎないようにしましょう。
2.文字がぎっしりと詰まっている本
本をパラパラと開いたときに、文字がぎっしりと詰まっていると読む気を損なってしまいます。
イラストや図表が入っていたり、また文字だけのページがあっても空行などがあることによってかなり印象は変わりますので、工夫して構成するとよいでしょう。
3.様々なコンテンツの詰め合わせになっている本
出版企画の段階では大まかな目次構成などを決めて本づくりをスタートしますが、本をつくり始めると「あのコンテンツも欲しい」、「あれも入れておかないと」と目移りしてしまうことがあります。
特に、初めて企業出版に取り組む場合にはコンテンツをいろいろと入れたくなる傾向にあります。
でも、様々なコンテンツを追加していくと、メッセージが伝わりにくくなってしまいます。
伝えたいことはできる限り絞って、効果を最も発揮しやすいような本を目指しましょう。
なお、目的に合わせてコンテンツを絞った本をすでに複数冊出版しているという場合は、あえて全体を包括的にまとめた本をつくるのも一手です。
4.誤字脱字があまりにも多い本
誤字脱字が多い本も世の中には存在しています。
多少の文字の間違いなどはそこまで気にならないかもしれませんが、1冊の本で10か所を超えるほどの誤字脱字が出てきてしまうと、間違いをチェックするような読み方になってしまって、内容への興味が薄れてしまいます。
企業出版は読んでくれた人の考え方、行動を変えることを目的としていますが、誤字脱字があまりにも多いと「この会社はいい加減な仕事をする会社だから取引はやめておこう」という逆効果の結論を下されてしまいかねません。
誤字脱字を減らすためには、複数人の目を通して何度も校正作業を行うことが最も効果的です。
AIが発達した現在であっても、最も効果的なのは人の目なので、本づくりを進めていく際には最後まで妥協なく誤字脱字を減らすよう力を尽くしましょう。
まとめ
今回は、企業出版の本に掲載するコンテンツ、そして読みづらい本の特徴について解説しました。
これから起業するという場合は例外ですが、これまでにサービスを提供していて満足してもらっているということは、サービスに魅力があることは間違いありません。
何をどのように伝えればその魅力を感じてもらえるのかについてコンテンツを考えていきましょう。
逆に言えば、企業出版はこれから起業する場合や、今までサービスを提供したことがない場合には不向きな施策です。
この場合は、WEB施策などでテストモニターを集めて安価でサービス提供するなどして、事例を集めるところからスタートすることをおすすめします。
【この記事のまとめ】
企業出版の本には自社独自の事例や経営者の話を盛り込むとよい
掲載順は普段の営業の手順にするのがおすすめ
誤字脱字やコンテンツの入れすぎに注意して読みやすい本を目指す
ラーニングスは企業出版専門の出版社ですので、目的に合わせてどんなコンテンツを盛り込むか、また読みやすい本を目指して原稿を推敲するお手伝いをしております。
気になった方はぜひお気軽にお問い合わせください!
企業専門出版のラーニングスがあなたの経営課題を解決します
\お気軽にお問い合わせください/
\出版に関する資料はコチラから/